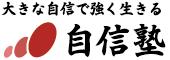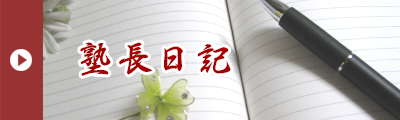関西大倉高校2年 Tさん【数学Ⅲ定期テスト99点・コース1位】
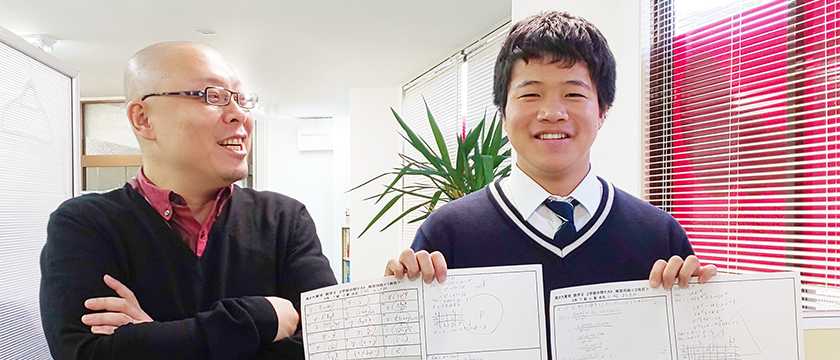
大久保先生の授業は、本当に分かりやすいです。大久保先生の言うことをちゃんと聞いて先生の言うことだけしっかりしていれば数学の成績は必ずあがると思い、信じて頑張りました。宿題は多くて指導も厳しいですが、頑張った結果がこの点数だと思います。
今回の中間テストの範囲は、数Ⅲの微分でした。全範囲の問題を理解することも頑張りましたが、特に、微分の計算を何度も練習し、これでもかというぐらい、グラフを書く練習を積み重ねました。はじめは、計算ミスをしていましたが、大久保先生に計算ミスの理由を毎回指摘されて、それを意識的に気にして計算するとミスがなくなってきました。グラフを書くのも、漸近線を考えたり、増減表を書いたり、極限をとったりといろんなことをしなければ書けませんが、「なぜしないといけないのか」という意味をちゃんと教えてくれたので、理解が出来てグラフがかけるようになりました。
テストの日は、帰宅してすぐに大久保先生に「3回見直しました、わからない問題はありませんでした!」とLINEしました。「さすが、Tさん!よくやった」と大久保先生から返事がきましたが、計算ミスしていないか不安でした。テスト返却の日、99点とわかったとき、とても驚きました、そして何より、今までの努力が報われた気がして、心から嬉しかったです。
今回99点がとれたことは、これから受験勉強をする上で何か辛いことが起こったときに「あのとき、あれだけ頑張っていい点がとれたからやればできるんだ!」という心のよりどころになると思います。
最後へ、数学が伸び悩んでいる人たちへ言いたいことがあります。
僕はミスをして悲しい気持ちになったとき、いつも大久保先生から「それだけミスしても、自分のことを見限ったらあかん!どうせできへん、とかゆうたらあかん!」と言われて勉強をしてきました。これは、本当にその通りだと思います。大久保先生は本当に厳しい人ですが、それは僕に期待してくださって僕の成長を待ってくれているからこそ厳しく接してくださっているのだと思います。だから、数学で伸び悩んでいる人も、今回の僕のように努力すれば必ずできるようになるので、諦めずに頑張ってください。
「どうせやってもできない」なんて思わずに頑張ってください。
僕も、希望する国立大学に入れるように、頑張ります。
保護者の声
「お母さん、数学のテスト99点で1番だった!あと1点。すごく残念だった!」
息子が学校から帰るなり私にそう言い、急いでカバンを開けて答案用紙を見せてくれました。先日の、2学期の中間テストの結果です。
これまで、息子は今まで自分からテストの結果を知らせてきたことはなく、自分の取った点数に対しても、大きく喜んだり残念がったりしなかったので、私はこの嬉しそうな彼の様子に驚き、(99点?1番?本当に?)と思いながら見ました。
「やったね!すごい!やっぱりちゃんと大久保先生が言われる通りにすればできたじゃない、がんばったね。おめでとう!」
思わず息子と握手をして喜びました。
「うん、できたんだ!ちゃんと見直しもできて間違いを見つけて直せたし、よかった~。」
息子はもともと、勉強があまり好きではなくやらされて仕方なくしていました。
これまでの試験も、自分ではできたと思っても返却されてみると計算ミス、問題の読み違い、時間切れで最後まで解けなかったなど、あれやこれや減点されなかなか良い結果が出せませんでした。
「もう勉強してもどうせ点取れないし、無理だ。」
と投げやりになり、やる気も失せ悪循環に陥りかけていました。
私は、やればできるという自信をなんとかつけてやりたいと思い、大久保先生に相談しました。先生も息子のこの様子に気づいておられ、いろいろと考えて下さっていました。
例えば、勉強だけでなくメンタルの部分でも支えて下さっていて、LINEで励ましのメッセージや、お手紙もいただきました。
息子はその大久保先生からのお手紙を勉強中よく見える所に貼っています。
高2になってからは息子のためにオリジナルの宿題プリントを作って下さり
「絶対に毎日続けること。このプリントをやらないなら授業はしない。」
と息子と厳しい約束をしてくださいました。
今まで何となくやらされて勉強していた息子が、このときから変わりました。
大久保先生の授業が受けられないのは絶対に嫌だし困るのです。
何が何でもこのプリントはするようになり、旅行にもこのプリントを持って行くほど彼の意識は変わりました。今もこの毎日の宿題プリントは続いています。
そして、テスト前には範囲の中で苦手な所やまちがえやすい所を何度も何度も繰り返し徹底的にして下さいました。
その結果が今回の99点です。先生も一緒にとても喜んで下さりそれがまた息子の励みにもなりました。
私が何より嬉しかったのは、彼がやればできると自分に自信を持てるようになり、勉強に前向きに取り組むようになったことです。
これから大学受験に向けてもっともっとハードな勉強をしないといけなくなります。そのためには、くじけそうになっても自分はできるんだと信じて頑張れる強い気持ちが必要です。
今回息子がこの事を実感できたのは大久保先生をはじめお世話になっている他教科の先生方やスタッフの皆さんのおかげです。
自信塾では息子のために先生、スタッフの方々が私とも密に連絡を取りながら彼に一番合った授業を組み、テストなどの結果や授業での様子を共有しこれらをふまえて今後の勉強方針を決めて下さり、何か改善すべき点が出てきたらすぐに修正して下さいます。
集団の塾では一人一人の生徒にこのような細やかな対応は難しいし他の少人数、個別指導の塾もいろいろ見聞きしてきましたが、ここまでして下さる塾は他にはなかなかありません。
実は2年前に娘も大久保先生にお世話になり志望大学の医学部に合格させていただきました。
先日その大学生の娘が、弟に話していました。
「何かあったらすぐに大久保先生に相談して。場合によってはめちゃくちゃ怒られるよ。その時は仕方ない、言われる通りにしなかった自分が悪い。でも言われる通りに頑張れば先生は何とかしてくれる。合格させてくれる。」と。
娘が合格した時、私も娘もこれを実感しました。
先生が与えて下さる課題は時に厳しいように見えますが、息子の合格を見据えてその時その時の彼に必要な内容になっていて、まさにオーダーメイドの授業と課題です。
これを「きちんとこなすんだ」という強い気持ちと、「やればできる」という自信を持って進むのが合格への近道だと思っていますので息子には今回の経験を忘れずに頑張ってほしいです。
先生、スタッフの皆様、どうぞこれからもよろしくお願い致します。
塾長からのコメント
塾長の大久保です
今回、僕の担当するT君が2学期中間テストで99点を取りました。
試験範囲は数学Ⅲの微分でした。
教科書と傍用問題集で先取り学習をしました。試験範囲の先取りはかなり早い段階で終わらせました。なぜなら、T君は普段から計算ミスがとても多くて、例えばグラフを書く問題など微分の計算ミスをしてしまうと、問題丸ごと点を落としかねない状況でした。ですから、試験範囲の学習を早く終え、計算力をつけさせないと点数に結びつかないので「早く計算練習をさせないと!」という思いでした。先取り学習を終えた後、試験範囲の重要問題を集めた彼専用の “重要問題プリント”を作りました。
予想通り、計算ミスのオンパレードでした。もちろん、彼は微分の計算の公式や考え方がわかっていないのではありません。むしろ、公式や考え方は完璧に理解していました。しかし、彼が実際にペンを走らせると、彼自身も「なぜ?」と思う計算ミスをしてしまうのでした。
こんなとき、僕の指導はいつも決まっています。これこそ、個別指導だからこそできることですが、彼が計算をしているときに横でずっと彼の計算過程を観察します。どのようなタイミングでどのような計算ミスを起こすのかを見つけます。そして、横で見ているときに彼が計算ミスを見つけても声はかけません。なぜなら、計算ミスは見直しをしたときに自分で発見して訂正できなくては意味がないからです。彼に計算をさせ、計算ミスがあってもなくても「あってるかどうか確認してみ?」と見直しを必ずさせます。これは、計算ミスを見つける訓練にあたります。また、見直しをするときも「正解していると思ってするんじゃなくて、間違ってるところがあると思って見直しなさい」と声をかけます。
その見直しをした後に指導が始まります。彼の微分の計算におけるミスが起こるタイミングと種類には、パターンがあることがわかりました。これを彼自身の答案を実際に見せながら、詳しく伝えます。じつは、これを教えることでとても大きな効果があります。彼が計算をしていてそのパターンが登場する場面になると、自然と計算に注意深くなります。すなわち、そこに落とし穴があるからゆっくり歩こう、と思えるのです。それを教えてから計算ミスの回数が格段に減りました。
さらに、このような数学的な話以外にも、彼にはこんな話もしました。「どれだけ数学の内容がわかっていても、どれだけ数学的に素晴らしい発想が出来ても、計算ミスをしてしまうと点数が取れないから無駄にしてしまう。もったいないって思わへん?」としつこいぐらい伝えます。(もちろん、これは “定期テストの点数を上げる”という意味でです。点数に結びつかなくても、数学を理解することや素晴らしい発想をすることには大きな価値があります。)つまり、これまでの努力を無駄にしないためにも、計算ミスは無くさないといけない、という気持ちを育てます。このような指導を、授業の度にしつこいぐらいに言い聞かせ、何度も何度も練習させていきます。
それでも、彼が計算ミスを全くしなくなったのではありません。その伝えたパターン以外に違う種類の計算ミスもしますので。しかし、僕が伝えた、多くの場合にあたる計算ミスにはかなり改善されました。試験前日に、“予想問題テスト”を実施し、試験と同じ時間で解いてもらいましたが、やはり計算ミスは起こりました。それでも、なぜミスが起こったのかを二人で検証して、「今夜もう一回この問題を解いて、それで明日を迎えなさい」と指導しました。
彼は見事に99点をとりました。あれだけしていた計算ミスは1つもありませんでした。
それは、なぜでしょうか。
彼は、どれだけ計算ミスをしても投げやりにならずに、何度も繰り返し練習しました。授業後も塾に残り、ひたすらグラフを書く練習をしているときもありました。何度も計算ミスをして、とても悔しそうにしているときもありましたが、「もう無理や」と諦めずに立ち向かっていった彼の強さが、本番で計算ミスをしなかったという結果を導いたのだと思います。また、僕の厳しい指導にもご理解してくださり、毎回塾への送り迎えをしてくださった保護者の方のご協力がなければなしえない結果でした。本当に感謝しております。
「次の期末試験も、クラスで1位をとります!」と彼は強気で僕に言ってくれました。この99点が彼にもたらしたものは、数学的な理解もそうですが、それ以上に「やればできる」と彼自身が思えたことだと僕は思います。これこそ、自己肯定感であり、僕が最も伝えたいものである「自信」です。
皆さんの中に、どうせ数学なんかできないと思っている人はいませんか?
T君みたいに、数学で自己肯定感を高められる人が一人でも多く増えることを期待しています。